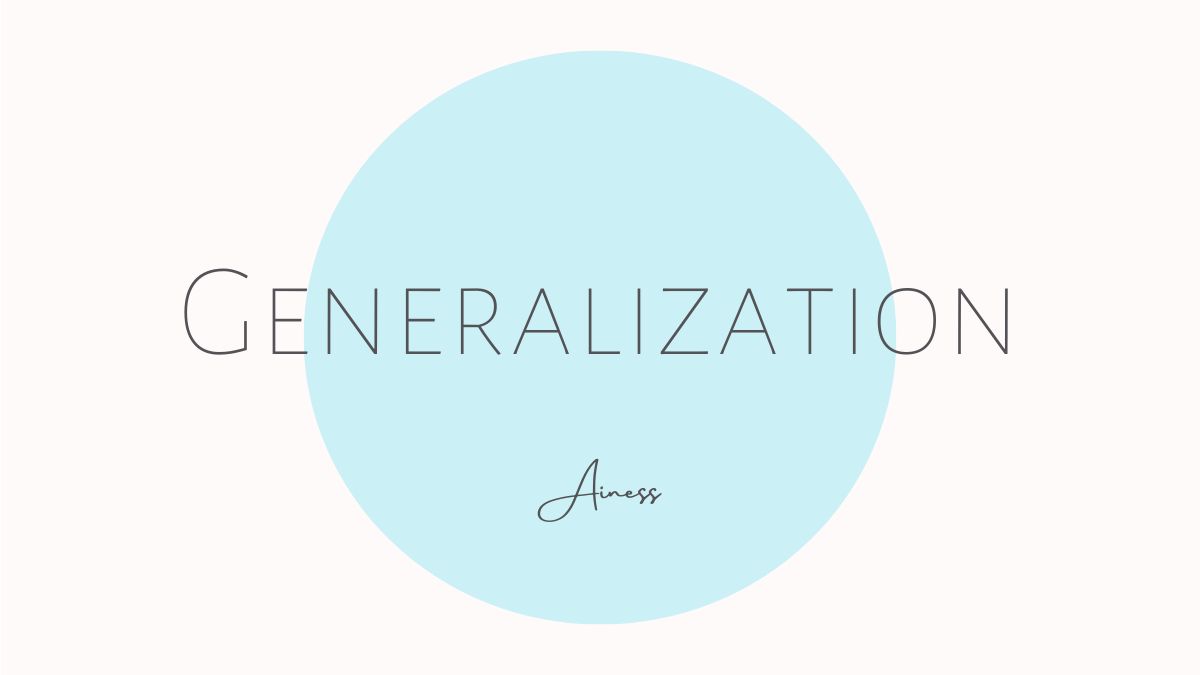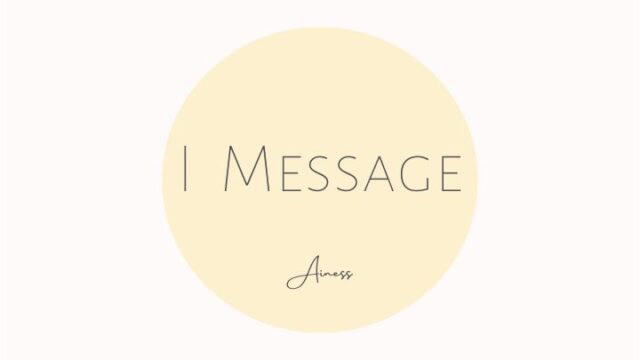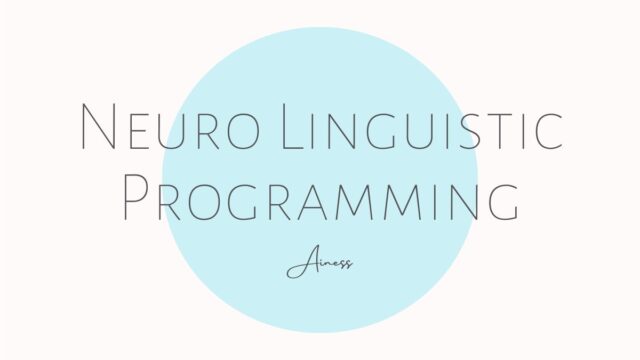一般化とは、新しい状況に効果的に適応するために、過去の経験や学習を元に共通点を見つけ出すことができる脳の働きの1つ。
| 名称 | 一般化 |
| 意味 | 抽象化の一形態。 1つの出来事(ケース・特徴・部分)を、全体を表すものとしてみなすこと。 |
| 英語 | Generalization |
| 訳 | 一般化 |
一般化とは
NLPにおける一般化は、新しい状況や環境にスムーズに適応するために、過去の経験や学習を元に、柔軟で効果的に行動ができるようにするための脳の働きの1つです。
過去の成功体験を、新しい挑戦や状況に適用しようとするなどがその例です。一般化の働きああることで、効果的に成長し、変化に対応することができます。
一般化の特徴
- 抽象化する:わずかな知識や経験を抽象的に捉えることで、汎用性があるルールや法則を素早く学ぶことを可能にする。
- 簡略化する:複雑なことを、シンプル化して認識させる。
- パターン化する:共通のパターンや法則に焦点をあて、それを他の事象にも広く適用する。
- 情報をフィルタリングする:膨大な情報を一般化することで、理解しやすくしている。
一般化のメリット
一般化をうまく活用できていると、以下のような特徴があらわれます。
- 物事の背景にある法則やパターンを掴むのうまい
- 理解力が高い&早い
一般化のデメリット
一般化が不適切に行われると、以下のような特徴があらわれます。
- 例外を考慮しない
- 柔軟性に欠ける
- 選択肢が狭められる
一般化の弊害
一般化は生きる上で大切な脳の働きですが、弊害として以下のようなことが挙げられます。
- 間違った一般化:過去の経験から得た一般化が、状況には当てはまらない場合があります。この場合、不適切な行動や判断につながってしまいます。
- 情報の欠落:一般化によって、特定の情報が省略されることがあります。これにより、重要な情報が見落とされる可能性があります。
- 想像力の制限:過去の経験に基づく一般化が強すぎると、新しいアイデアや行動の選択肢に目をむけることが難しくなることがあります。創造性や革新性を阻害する可能性があります。
- ステレオタイプの強化:一般化によって、ステレオタイプや偏見が強化される可能性があります。これは、社会的な偏見や不平等を助長する可能性があります。
- 感情の抑圧:過去の経験に基づく一般化が強すぎると、現在の状況に対する感情的な反応が抑圧される可能性があります。これにより、人生の豊かさや幸福感を感じにくくなる可能性があります。
以上のように、一般化には弊害があるため、適切な行動・選択ができるように注意する必要があります。NLPなどの心理学的技法や、批判的思考や問題解決力の向上などの思考能力の開発により対処することができます。
一般化の例え
- 私には“できません”。
- 彼はいつも正しい。
- 人に迷惑をかけるべきじゃない。