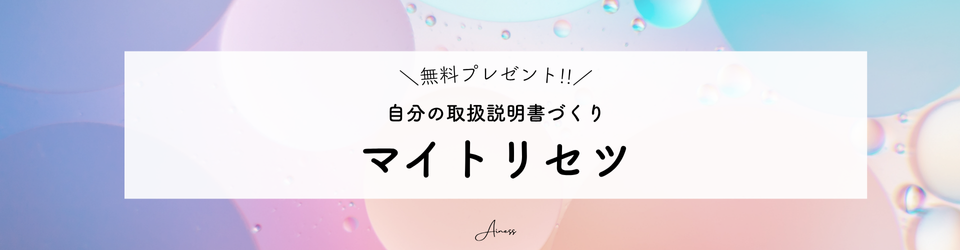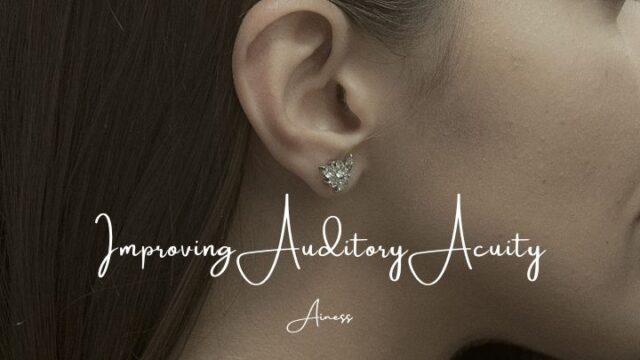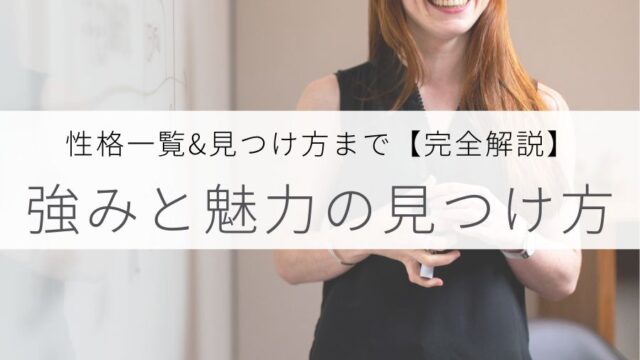現代社会において、デジタル化の加速や移動手段の発達により、私たちは触覚や運動感覚を使う機会が激減しています。いつも同じ触感のスマホやタブレット、キーボードにだけ触れ、無機質な建物や空間、調整された空調、人工的な物に囲まれて過ごし、身体も決まった姿勢でいる時間が長く、動きも限られていることが大半ですよね。
その結果、身体を通して「感じる」力が鈍化することが懸念されています。本来、触覚や運動感覚は、身体の健康や精神的な安定にも必要不可欠な力で、積極的に感じる力を磨くことが重要です。
この触覚(触れることで感じる力)と、運動感覚(身体の緊張や運動によって感じる力)を合わせた感覚を「触運動覚」と言います。今回はこの触運動覚力を高めるメリットと、その方法をご紹介します。あなたはどれだけ「身体感覚」に意識が向いているでしょうか?ぜひ自分と照らし合わせて読み進めてみてください!
身体感覚に優れた人の共通点

私たちは手や足を使って物を触ったり、身体に触れたりすることでそれがなんであるかを認識したり、自分にとっての心地よさ/心地悪さを感じたりしています。また身体を動かすことで、重心を感じる、バランスを調整する術を身につけています。また身体が緊張状態か??リラックス状態か?を感じることで体調や感情の様子をモニタリングしています。
これらの身体の感覚を感じる力を高めることは、健康、精神的な安定、パフォーマンスの向上に欠かせないものです。しかし現代社会では意識的に取り組まなければこの感覚を鍛えることが難しいのが現状です。感覚の鋭敏性を高めることは自身の幸福感、充実感、達成感などの「感じる」能力の基盤となるものです。
身体的な感覚への感度が高い
触運動覚に優れた人は、自分自身の身体的な感覚に注意を払うことができます。たとえば、姿勢や呼吸、筋肉の緊張度合いや、リラックス度合いなど。また身体の様々な部位の動きを繊細に感じ取ることができます。このため運動の正確性やバランス感覚が優れていることが多いです。身体的な感覚を敏感にキャッチすることができ、またそれに反応することができるのですね!
また外部との接触、触れたものからの刺激にも敏感です。質感や硬さ、形状などから、物質の種類や状態を判断することができます。これは経験に基づく知識があるためです。
身体の細かい違いや変化を捉えられる
触覚の感覚が優れた人は、指先で微細な刺激を感じることができるため変化や違和感を細かく感じ取ることができます。衣服の肌触り、風の強さや方向、温度の変化など、細かい変化に敏感です。
身体的な心地よさを知っている
身体的な感覚として何が心地よいか、気持ち良いかを理解しています。
身体感覚に没頭することができる
身体感覚に没頭することができます。たとえば、ダンスやヨガのポーズ、スポーツの技術など、細かい動作にまで注意を払って練習することができます。自分がイメージした通り、思う通りに身体を動かすことが得意であったり、細かい動作にまで注意を払って表現することが上手であることも多いです。
身体的な調整力が高い
運動感覚が優れた人は、視覚情報を身体感覚や運動に統合することができます。このため、目的地に向かって運動する際に、周囲の状況や障害物を的確に判断して、スムーズに動くことができることが多いです。
また身体の各部位の動きを調整して動くことができます。複雑な運動を行う際にも、スムーズに動くことができることが多いのもそのためです。
身体感覚を高める方法

身体感覚の感度が高いとき、触れたものについての細やかな質感や、自身の緊張/リラックス状態の違いや変化などに敏感に気がつくことができます。それは細かく、繊細に刺激を認識する経験を積み重ねてきているからです。そしてそれは誰でも後天的に身につけることができるもので、同じようにそこに意識を向ける経験を積み重ねることで鋭敏性を高めることが可能です。
⑴ 身体感覚を細かく理解する
身体感覚(触運動覚)をここでは3つに分けてご紹介します。身体の感覚にもさまざまなものがありますよね。
- 触れる感覚(触覚)
- 筋肉の感覚(筋肉記憶)
- バランスを司る感覚(平衡感覚)
自分はどの感覚については鋭敏で、どの感覚については鈍感/もしくは無視しているでしょうか?

⑵ 触運動覚のサブモダリティを知る
「触運動覚情報」は「圧」「範囲」「温度」「肌触り」などさまざまな要素から成り立っています。これら触運動覚を構成する細かい要素のことを触運動覚のサブモダリティと言います。あなたは普段どれには意識が向いていて、どの要素にはあまり意識が向かず感じていていないでしょうか?
- 位置・場所がどこか
- 重心がどこか
- 強い⇄弱い(強度)
- 広い⇄狭い(範囲)
- かたい⇄柔らかい(圧力)
- 粗い⇄なめらか(肌触り)
- 重い⇄軽い(重さ)
- 冷たい⇄熱い(温度)
感覚の細かい要素(サブモダリティ)とは?↓

触運動覚のサブモダリティ↓

⑶ 意識的にトレーニングする
日常的に身体の感覚に意識を向けるトレーニングが効果的です。
運動やストレッチ
身体感覚を高めるために、身体を動かすのはもっとも効果的。ウォーキングやランニング、ヨガ、水泳、ダンスなど自分に合った運動をライフスタイルに取り入れるのが効果的です。
また身体の伸びや強張りといった状態を感じ、ほぐすためにはストレッチがオススメです。ストレッチをすることで身体の柔軟性を高めるだけでなく、細かい部位の動きを繊細に感じるトレーニングになります。
瞑想や呼吸法
静かな場所で、感覚にだけ集中する機会として瞑想や呼吸法が挙げられます。身体の感覚だけに意識を向け、身体感覚を磨くのに瞑想や呼吸法は最適です。深く呼吸をすることで筋肉が緩む感覚、リラックスする感覚など普段あまり意識が向かない変化を感じる練習になります。また本来のリラックスしている状態を掴むのにもすごくオススメです。
マッサージ
身体に触れた感覚、触れられた感覚を細かく感じることで、指先の感覚、そして全身の(肌で感じる)感覚を磨くことができます。毎日お風呂上がりにセルフマッサージをする、身体に触れるだけで感覚は変わっていきます。
バランス感覚を感じる
目を閉じて真っ直ぐに立つことや、バランスボールを使うことで、身体の中心に重心を持っていく感覚を掴むことができます。
自然に触れる
自然に触れることも、感じる力を磨くのにとても大切です。自然の中に入ると、人工物に囲まれている時とはまったく異なるさまざまな刺激を受け取ります。
いろんなものに触れてみる
さまざまな質感のものを触ることで触覚感覚が磨かれます。木の質感、石の質感、紙の質感、シルクの質感、麻の質感…など素材や物によって感じる感覚は異なります。いろんなものを触ることで、触覚感覚のデータを増やしていきましょう。
⑷ 触運動覚を活用する
触運動覚を使って、思考や感情に訴えかける
触運動覚に関する細かい違いを認識する力は、自分の状態を知り調整するという心身の健康面にも役立ちますし、身体表現を通して豊かなコミュニケーションを取ることで人間関係の構築にも活用することができます。
例えば、自分の身体の感覚を鋭敏に感じ取ることで緊張状態から意図的にリラックス状態へと調整することは、とても大切です。またどの部分に力が入りやすいのかを理解できることで、そこを重点的にケアすることで疲れにくい身体を作ったり、常にいい状態でパフォーマンスが出せるコンディショニングができます。
またコミュニケーションの際も、内容を「情報」として伝えるだけでなく、自分の感覚や動きを文章にしたり表現することで、感情や感覚をより明確に相手に伝えることができます。(手を広げて喜びを表現する、手を叩いて笑うなど)
まとめ

触覚や運動感覚を高めることは、身体の健康や精神的な安定につながるだけでなく、日常生活においても役立ちます。
日常生活のちょっとした場面での工夫で、これら「感じる力」を高めることができます。一駅分を歩く、エスカレーターではなく階段にする、お風呂に入っているときに身体を5分だけマッサージする…といったように。
またスポーツやヨガ、ストレッチなどの運動をライフスタイルに取り入れることで、運動感覚が鍛えられるだけでなく、ストレス解消や健康維持にもつながりますね。さらに、自然に触れる機会を増やすことや、料理や手芸などの手先を使う趣味を楽しむことも、触覚を刺激する良い方法です。
この感じることに敏感になればなるほど、自分の感覚、気持ち、心地よさ、心地悪さも鮮明に分かるようになるため「自分に合う/合わない」という自分軸を磨くことにも繋がります。ぜひ積極的に「感じる」習慣を身につけてみてください!
さらに自己理解を深めたい方へ
「もっと自分のことを深く知りたい」そんな方へ。
20分で自己理解を深めるワークをお届けしています。
✔︎ 人生の流れをグラフで描いて整理
✔︎ 思考・感情のクセに気づける
✔︎ 自分らしい人生のストーリーに気づく
▶︎[マイトリセツワークを受け取る]
📝 気づきや決断を、書き出してみる
言葉にすることで、自分との対話が始まります。
記事を読んで感じたこと、明日から意識してみたいこと、そんな“小さな気づき”を、今ここで書き留めてみませんか?
▶︎ [リフレクション・フォーム](メールで受け取りたい方)
▶︎ [リフレクション・ワークシート](PDF/紙で書きたい方)
▶︎ [Ainess Library 活用ガイド](記事の効果的な読み方)
📘 関連記事をもっと読む
読むだけで“視点”が増え、日常に活かせるヒントが見つかる。
自己理解・感情・思考・行動のテーマを掘り下げたnote記事を公開中です。
▶︎ [note記事一覧を見る]
✅自分らしい人生を整えるヒントを受け取る
自己理解や変化のヒントをLINEでもお届けしています。
新しいワークや限定コンテンツの優先案内もLINE登録者限定で配信中です。
▶︎ [LINE登録はこちら]